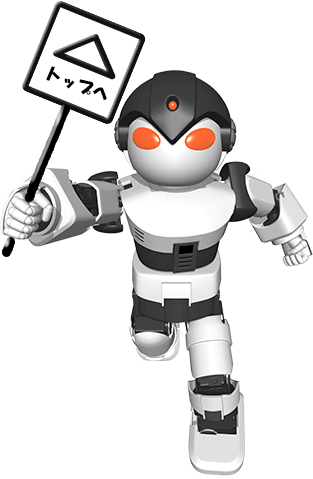2025年4月23日東京ビックサイトで開催されている「EDIX Seminar東京」に行ってきました!
以前からお話を聞きたかった岡田監督が携わっている「FC今治」の教育について非常に興味深いお話が聞けました。また、木村先生の熱く心に訴えかけられたお話も印象的で、日本の義務教育の抱える問題、そして今後、大人はどういうスタンスで子供たちに向き合えばいいのか課題が浮かび上がりました。「主体性」「自主性」」「当事者性」が強いキーワードとして心に突き刺さりました!以下、要約を掲載いたします。
日本社会が抱える課題は、学校教育の課題そのもの。管理型の教育システムは、子どもたちの「主体性」と「当事者性」を奪い続けている。本セッションでは、登壇者3人が、それぞれの実践事例をもとに、今求められる教育のあり方を議論し提案する。
<プロフィール>
●岡田 武史
早稲田大学政治経済学部卒業後、古河電気工業株式会社に入社。2度のW杯で指揮を執り、南アフリカ大会ではチームをベスト16に導く。Jリーグや中国リーグでも監督を歴任した。現在はFC今治の運営会社、株式会社今治.夢スポーツの代表取締役会長として「次世代のため、物の豊かさより心の豊かさを大切にする社会づくりに貢献する」を企業理念として、サッカー事業だけでなく環境教育事業や学校法人の運営など様々分野で活動している。
- 工藤 勇一
公立学校教員、東京都教育委員会、新宿区教育委員会指導課長を経て
千代田区立麹町中学校長(2014年4月〜2020年3月)
横浜創英中学・校長学校長(2020年4月〜2024年3月)
内閣官房教育再生実行委員(2018年8月〜2021年8月)
【2025年2月現在】
内閣府規制改革推進会議専門委員(2021年8月〜)
他、自治体やFC今治高校里山校や東明館学園など、私立学校のアドバイザーを務めている。 - 木村 泰子
大阪府生まれ。2006年に開校した大阪市立大空小学校の初代校長を9年間務める。大空小学校では「すべての子どもの学習権を保障する」という理念のもと、教職員や地域の人たちとともに障害の有無にかかわらず、すべての子どもがいつもいっしょに学び合っている。2015年には大空小学校の1年間を追ったドキュメンタリー映画「みんなの学校」が公開され、大きな反響を呼んだ。この映画は文科省の特別選定作品にも選ばれ、現在も全国各地の教育現場などで自主上映されている。2015年春に、45年間の教員生活を終え、現在は講演活動やセミナーで全国の人たちと学び合っている。
内容:
これからの時代を生きる子供たちには主体性・自主性と当事者意識が大事。岡田さんが教育事業に携わっているとき、教師には子供たちに「どうしたの」「どうしたいの」「何か手伝えることはある?」この3つの言葉がけで子供たちに寄り添うことを心掛けている。エラー&Learn 失敗していいし、やり直す自由が認められている。
生きる力とは、変化の激しい現代やこれからの時代を生き抜くため、自ら課題を見つけ主体的に判断し、行動し問題解決していく力。(文部科学省)
現在、不登校は40万人、自殺者は年間529人。15歳以下の死因の半分以上が自殺。
日本政府は国連から勧告されている教育虐待の国・理由は
1・過度な競争と圧力
2・画一的な教育と批判思考力の欠如
3・生徒への多様性の対応不足
4・教員へのサポート不足
そもそも世界には高校受験はない。日本と韓国が過度な受験戦争を繰り広げている。
大阪大空小学校の初代校長・木村先生は、子供は生まれた時は全員が主体性を持っている。赤ちゃんはソファーがあったら上ろうとするし、引き出しから色々引っ張り出したりする。ところが育つうえで、質問が出来なくなる「これやっていい?」「トイレ行っていい?」臆病になっている。自分でそれが判断できていない。教師は生徒からこの質問があったときに「いいよ」といってはNG。なぜなら、他人の判断待ちで動けない人になってしまうから。主体性・自主性が育まれない。
立命館大学とFC今治が提携しているのは、FC今治のような教育で育った生徒はどのような人間としての素養が育っているのかをリサーチしている。今後、チャットGPTで100点取れるようなことを入試で競わせることが果たして国際競争力のある素晴らしい人材を育てることになるのか、また現状AOで入学したわりにパッとしない生徒が多いので、面接とかでは計り知れない素養をどうやって判断していくのかといったところが大学として知りたいところになっている。
日本の教育は言うことを聞く人を育てている。「~していいですか?」と必ず聞いてくる。ところが欧米では自己決定をしながら育っているからコーチの指示にも「なぜですか?」と質問してくる。サッカーのような瞬間で判断しなければならないスポーツでも日本の選手は指示通りに動くことしかできない。欧米のように判断を選手に任せると迷ってしまいサッカーで勝てなくなってしまう。
次世代子供達が生きていく時代は、親世代の私たちが知らない世界だから歩いたことの無い親・私たちは子供たちに指導できることは何もない。子供たちは適応力を身に付けコミュニテイーを作り自分事化していく力をつけていくことが教育現場で求められていくことである。
米大リーグで活躍する大谷翔平(ドジャース)と菊池雄星(エンゼルス)の2選手を育てた岩手県の花巻東高校野球部・佐々木洋監督は、異才を育てるカギは「目標設定」にあると言い切る。(日経3/29より)
「人材育成方法は野球から学んだことより経営や異業種から学んだことの方が多い。非常識にものを考えることもその一つだ。野球は経験論が受け継がれている。髪形を丸刈りに統一するのはなぜか。走り込みをすると下半身に本当に強い筋肉がつくのかなど、全てを一度疑うことを指導の基本にしている」
――経営や異業種から、野球指導に生かした学びとは何か。
「監督になってすぐのころ、県内の大会で負けた時に、『経営を学べ』とある恩師から言われた。当初の私はマネジメントという言葉を知らなかったし、なぜ自分の学校に良い選手が来ないのかもわからなかった。ただ、生徒という顧客からみれば、当時はプロ選手や大リーガーはもちろん、大学進学も就職も実績がなかった。これでは顧客は来ないと気づいた」
「そこでまずは出口戦略から始めた。良い選手を集めるよりも、まずはきちんと教育して、大学や企業が欲しがる生徒を育てることを自身の目標に据えた。成果が出始めると、優秀な選手が入学するようになり、チームも強くなっていった」
「私が野球の指導者になることを決めたのは大学生の時だ。漠然とプロ野球選手になる夢を抱き関東の大学の野球部に進学したが、20歳の時に学生寮からの退寮を迫られた。中途半端な自分に嫌気がさしていたころ、米国の哲学者であるナポレオン・ヒルが書いた『思考は現実化する』という本を読んだ。その時、なりたい自分と自らの行動がずれていることに気づいた。そこで初めて自分で目標設定をしてみて、その重要性に気づいた」
「親も監督も、子どもが目標や進路を定めるように導いてあげるのが仕事だ。『自主性』という言葉があるが、一歩間違えるとただの放任になってしまう。子どもたちが自主性と主体性を持つためには、目標設定の仕方をしっかりと教えることが重要だ」
「感染症と同じように思考も周囲に感染すると思う。子どもたちには『良い思考を持つ人と濃厚接触し、他人や環境のせいにする思考の人とはソーシャルディスタンスを保ちなさい』と呼びかけている。他人のせいにする思考を捨てる人が増えれば、この国は大きく変わるのではないか」
――目標を細かく設定するのは、大谷選手のようなトップ選手はできるかもしれないが、普通の子どもたちには難しいのでは。
「数学の勉強よりも、よほど簡単なことだ。ただ目標の立て方がわからない生徒もいるのは確かだ。たとえば野球部では具体的な質問形式のシートを使っている。『全国でのライバルは誰か』『なぜその選手を選んだのか』『その人に勝つためにどうするか』とか。質問に答えるうちにやるべきことが明確になる」
「こうした目標の立て方は小学校で教えるべきで、子どもが習得すべき最も大切なことだ。それが優秀な人材を育て、国の発展にもつながると思う。限界は自分や大人など周囲がつくり上げているだけで、非常識と感じる夢でも目標を掲げることで一歩ずつ近づく」
――日本の学生は「将来の夢を持っている」と答えた割合が世界と比べて低い。この水準を高めるのは容易ではない。
「息子の麟太郎がスタンフォード大に進学する時に、菊池から勉強になる話を聞いた。『日本は減点法で、米国は加点法。日本人は平均的な人材をつくりたがる』と。麟太郎は国内では『守れない』『走れない』と言われたが、米国では長打力をとても褒められた。私も含め日本の指導者は弱点を批判する。日本も長所を伸ばす文化に変わらないといけない」
「私は今の日本に強い危機感を持っていて、優秀な日本人だけ米国に流出する可能性があると思っている。野球でいえば、米国の大学はトレーニング施設や食事のサポートなど環境が抜群に整っている。魅力ある大学をつくらないと、優秀な選手が米国の大学に流出してしまう。稼げる人材にとっては日米の給与の差も大きい。これはスポーツに限らない日本の空洞化の危機だ」「親や指導者が世界の現状を見せる機会をつくることも大事だ。学校であれば、お金がなくても自治体の援助を利用して積み立てをしたり、海外の姉妹校を活用したりとか工夫すべきだ。一度、行って帰ってくれば子どもの意識と意欲は変わるだろう」